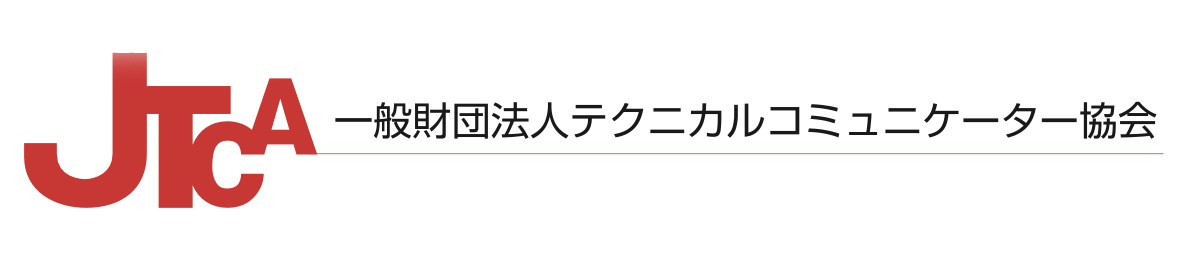テクニカルコミュニケーションとは
テクニカルコミュニケーションは、技術的知識、経験、立場が異なる人々のコミュニケーションを円滑に行うための技法です。技術情報をつくり、届け、つかっていただくプロセスでもあります。次のような用途と目的で用いられています。
- 複雑な情報を整理したり、文章や説明図として可視化したり、伝達したりすること
- トリセツ(説明書)、マニュアル(手順書)と呼ばれる情報をつくり、利用者に届けること
- 利用者の誤解や間違いを減らすこと
- 利用者の理解を助けたり、行動を促したりすること
- 安全に、効果的に、効率的に製品やサービスを利用していただくこと
テクニカルコミュニケーションは、語彙、要求、評価軸、情報の内容と媒体の設計について、国際規格として標準化されている技法です。情報の作成、提供、管理が法令で義務付けられる場合には、法令要件を満たすために用いられます。
- 語彙:ISO 24183:2024-01『Technical communication - Vocabulary』
- 要求と評価軸:IEC/IEEE 82079-1:2019-05『製品の使用情報(使用説明)の作成ー第1部:原則及び一般要求事項』
- 内容と媒体:JIS X 0153:2024(ISO/IEC/IEEE 26514:2022)『システム及びソフトウェア技術ー利用者用情報の設計及び作成』
- 関連法令:製造物責任法(PL法)、景品表示法など
テクニカルコミュニケーションの技法
テクニカルコミュニケーション技法とは、情報をつくり、読み手に届け、つかっていただくプロセスにおいて必要となる下記の知識と能力の総称です。
- 説明対象の製品やサービスの仕組み、機能、提供価値を理解する力
- 技術情報を収集し、必要な情報を抽出し、整理する力
- 法令に書かれている要件、規格として体系化されている要求を読み解く力
- 技術、仕様、法令要件、規格要求に適合する情報の中身と媒体を設計し、表現する力
- 製品、サービス、情報を利用する人々や組織のリテラシー、目的、立ち位置を理解する力
- 日本語や英語で文章を書く力、説明図を描く力、構成する力、デジタルツールを使う力
テクニカルコミュニケーションの特徴
テクニカルコミュニケーション技法には下記の特徴があります。他のコミュニケーション技法では他人の著作物の書き換えを抑止するのに対して、他人の著作物を書き換えることを用途に据えているところは顕著な特徴です。
- 技術者など他人の著作物を、読み手と目的に即して書き換える技法
- 法令要件に即した、規格要求に基づいた情報を、つくり、届け、つかっていただくための技法
- 正確性を重んじ、これを担保し続けるための技法
- 信頼性を堅持するために、トレーサビリティー(追跡可能性)を確保する技法
- 理解される(つたわる)ようにつたえるための技法
- 属人性を排除するため、構造化され、標準化された技法
- 標準工程モデルを推進する技術
テクニカルコミュニケーション技法が属人性を排除した技法であることは、次の実績が示唆しています。
- トリセツやマニュアルとして知られている利用者用情報が、書き手や作り手が変わっても長年にわたって均質な品質を維持し続けてきていること
- 発信する組織が異なっていても、製品やサービスに違いがあっても、だいたい同じような構造、表現術、情報管理プロセスでつくられ続けていること
テクニカルコミュニケーションは誰が使う技法なのか
たとえば、テクニカルコミュニケーターと呼ばれる専門職は、一般にトリセツ(説明書)やマニュアル(手順書)として知られている利用者用情報をつくり、届け、つかっていただくために、次のような専門的知見を知識化し、構造化し、標準化しながら業務に活用しています。テクニカルコミュニケーション技法はテクニカルコミュニケーターの研鑽によって変化し続けています。
- 技術情報や仕様情報を、利用者や目的に合った利用者用情報につくり変える技能
- 文章や説明図を、利用者用情報の構成要素として個別につくるための表現術
- 要素を、利用者視点で適切に配置して、伝達の効果を高める技術
- 文字、文章、図、動画、音声など多様な表現要素を、適切に組み合わせて媒体に仕立てる技能
- 媒体を、利用者に適切に届ける技術
- 利用者用情報を、製品やサービスのライフサイクルに沿って維持管理する技能
- 利用者用情報の品質を、法令や規格に照らして安定させる知識と技能
- 製品やサービスの開発者とのコミュニケーションを円滑に推進する技能
- プロジェクト管理に必要な工程を、設計して運用する技能