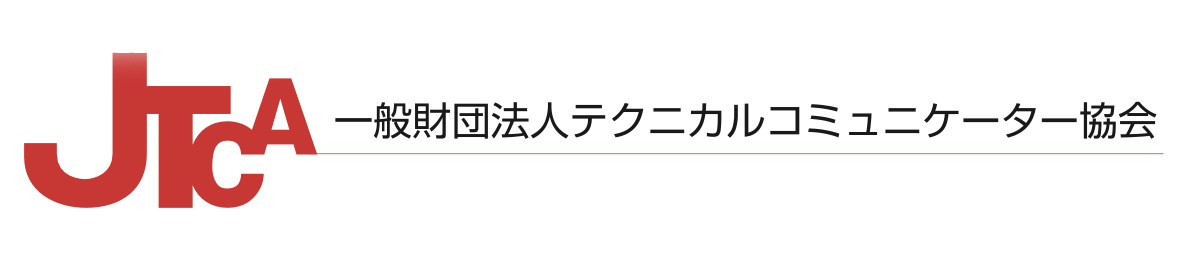用語集
説明書(トリセツ)とは
説明書とは、製品がつくられ、販売され、つかわれ、リサイクルされたり廃棄されたりするまでを通じて、利用者が安全に、効果的に、かつ効率的に利用するための概念、手順、参照情報を提供する情報を指します。一般にトリセツ、マニュアルなどと呼ばれているものですが、最新の国際規格および日本産業規格では利用者用情報と呼ばれます。
利用者用情報とは
利用者用情報とは、印刷物としての説明書およびデジタル情報の総称です。利用者が安全に、効果的に、かつ効率的に利用するための概念、手順、参照情報を提供する情報です。利用者用情報は供給者によってつくられ、製品の一部として利用者に提供されます。印刷された説明書だけでなく、画面上の情報、ソフトウェアの一部として組み込まれている情報を含みます。さらに、画面上の利用者用情報においては、利用者が作成したコンテンツを取り込んだり、利用者が二次加工して利用したりすることも想定します。
利用者用情報は、紙、製品に貼られたラベルや銘板、製品の包装、Webサイト、アプリ、ソフトウェアに組み込まれた状態など、さまざまな媒体や場所で提供されます。カタログに掲載されることもありますが、同じカタログに掲載される価格情報、および購買意欲を促すための販促情報は利用者用情報には含まれません。利用者用情報(の作成コスト)は製品の一部として製造原価を構成しますが、価格情報と販促情報(の作成コスト)は製造原価に含めることはできないからです。
なお、JTCAが2018年から製品・サポート情報と呼んできたものは利用者用情報と同じです。2024年の日本産業規格化を契機として、JTCAは利用者用情報に順次統一します。
- 利用者用情報:JIS X 0153:2024(ISO/IEC/IEEE 26514:2022)『システム及びソフトウェア技術―利用者用情報の設計及び作成』
- 『製品・サポート情報のつたえかた:コンプライアンスと校閲編』
https://jtca.org/learn-tc/publication/guide_dr_cp/ - 関連法令:製造物責任法(PL法)、薬機法、改正個人情報保護法、労働安全衛生法、サイバーセキュリティ基本法、デジタルプラットフォーム取引透明化法、AI法、景品表示法など
説明書(トリセツ)のつくりかた、利用者用情報のつくりかた
説明書、つまり利用者用情報のつくりかたは、国際規格や日本産業規格に詳細に述べられています。デジタル化された利用者用情報は、ソフトウェアのライフサイクルプロセスの一部として設計され、つくられ、管理されます。デジタル化されていない利用者用情報も、デジタル化された利用者用情報と同じソフトウェアのライフサイクルプロセスの一部として設計し、つくり、管理することもできます。
- 利用者用情報のつくりかた:JIS X 0153:2024(ISO/IEC/IEEE 26514:2022)『システム及びソフトウェア技術―利用者用情報の設計及び作成』
- 要求と評価軸:IEC/IEEE 82079-1: 2019-05『製品の使用情報(使用説明)の作成-第1部:原則及び一般要求事項』
- 制作実務と管理実務の参考書:『日本語スタイルガイド(第3版)』
『製品・サポート情報のつたえかた:コンプライアンスと校閲編』 注:2018年刊行当時の法令規格に基づく内容
『トリセツのつくりかた:制作実務編』 注:2010年刊行当時の規格に基づく内容
『トリセツのつくりかた:品質追求編(新編集版)』 注:2015年刊行当時の規格に基づく内容
https://jtca.org/learn-tc/publication/
取扱説明書とは
取扱説明書とは、製品と利用者と意図する使用(供給者が想定する用途)を特定する情報、安全情報、故障時の対応方法、輸送や保管の方法、組み立てや設置の方法、メンテナンスの方法、廃棄の方法を記載した印刷された文書、またはその代替物(PDF)を指します。製品の一部として、製品出荷時に完成された状態、かつ文書構造で提供することが法令や規格で義務付けられています。
取扱説明書(取説、説明書と略して呼ぶこともある)は、かつては、印刷された利用者用情報と同じ意味を持っていました。しかし、最新の国際規格および日本産業規格では、取扱説明書の記載内容と媒体を限定しています。
- かつての取扱説明書:1995年の制定以来、取扱説明書の拠り所となっていた国際規格(ISO/IECガイド37)は、2022年に廃止された。
- 現在の取扱説明書:ISO 20607:2019 『機械類の安全性―取扱説明書―起草のための一般原則』
- 取扱説明書の位置づけ:ISO 12100『機械類の安全性―設計の一般原則―リスクアセスメント及びリスク低減』
- 関連法令:製造物責任法(PL法)、薬機法、労働安全衛生法、サイバーセキュリティ基本法、景品表示法など
使用情報、使用説明、情報製品、製品情報、マニュアル
使用情報、使用説明、情報製品は、要求と評価軸を述べているIEC/IEEE 82079-1:2019で定義された用語です。利用者用情報とほぼ同じものを指していますが、利用者用情報とは違い、利用者が作成したコンテンツを取り込んだり、利用者が二次加工して利用したりすることは含みません。また、使用説明は紙媒体またはその代替物(PDF)を対象に用います。
使用情報については、JIS X 0153:2024において、利用者用情報を優先用語とする旨が定められています。使用説明については、これまで容認用語とされていましたが、JIS X 0153:2024において削除されており、利用者用情報(または使用情報)にすべて置換する旨が定められています。
製品情報は、一般に製品に関する情報を指す、法令や規格における定めのない言葉です。商品情報も同じです。法令規格で別扱いとなる取扱説明書とカタログを総称したいときの用例が多いようです。 マニュアルは、手順を記載する手引書を指す外来語として用いられていましたが、いつしか説明書と同じものを指す和製英語として定着しました。しかし、機械やAIを用いる自動作業に対して人手で行う作業をマニュアルと表現する用例が増えており、特に海外で顕著です。JTCAは利用者用情報に順次統一していきます。
- 要求と評価軸:1995年の制定以来、取扱説明書の拠り所となっていた国際規格(ISO/IECガイド37)は、2022年に廃止された。
- 利用者用情報のつくりかた:JIS X 0153:2024(ISO/IEC/IEEE 26514:2022)『システム及びソフトウェア技術―利用者用情報の設計及び作成』