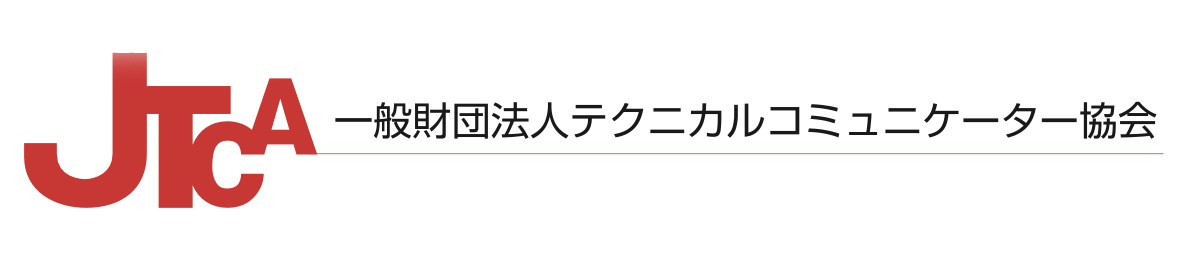23-CD09 【特別セッション】国語力低下時代、いかにして正しく伝えるか(2023.8.17更新)
セッション時間 8月24日(木)13:30-15:45
対象とする聴講者
ディレクター、ライター、管理者
セッションの企画意図と概要
子どもたちの国語力、読解力が低下しているという話題をたびたび目にする。文部科学省の定義によると、国語力とは「考える力」「感じる力」「創造する力」「表す力」の4つの中核からなる能力とされる。教科書を正確に読めない子どもや算数の文章題が解けない子どもが増えていることも、研究者たちにより明らかになっている。その現象はゆとり世代以降のZ世代から顕著になっているという調査結果もある。また、文科省の「全国学力・学習状況調査」の結果からも、取説でよく使われる構文の読み間違いが多いことがわかる。本人は読めているつもりでも、実際は理解していない現象が起きているのだ。そのような子どもたちも大人になり、ユーザーになる。我々TCは、どのようなユーザーにも正しく取扱情報を届けなければいけない。認識や発想の転換も必要になるだろう。
一方、大人の国語力はどうだろうか。ほとんどの企業は入社試験で重要視する要素として「コミュニケーション能力」を挙げている。コミュニケーションは複数の能力の総合体だ。文部科学省では、その総合的な能力を「国語力」と呼んでいる。人は獲得した語彙をベースに、自分の感情を分析して感じ取り(情緒力)、他者の気持ちや見知らぬ世界を思い描き(想像力)、物事の因果関係を思い描く(論理的思考力)。つまり、コミュニケーションがうまくとれるかどうかは、お互いの国語力に左右されるのだ。ベテラン世代と若手世代、我々TCとユーザーに生じる「ギャップ」も国語力の違いからくるのではないだろうか。
そこで本セッションでは、『ルポ 誰が国語力を殺すのか』の著者であり、国語力に関して精力的に取材し、執筆活動を行っている石井 光太氏を講師に迎え、子どもの国語力、大人の国語力の現状を把握して理解するとともに、正しい情報を届けるにはどうしたらよいか、円滑なコミュニケーションをとるには何が必要なのかを探りたい。
■講義の流れ
- 今、子どもたちの国語力はどうなっているのか
- 大人の国語力-世代によって異なる国語力
- 質疑応答
※ 本セッションは、配布資料はございません。
講師
石井 光太 作家
プロフィール
1977年、東京生まれ。国内外の貧困、災害、事件などをテーマに取材・執筆活動を行う。作品はルポ、小説のほか、児童書、エッセイ、漫画原作など多岐にわたる。著書に『物乞う仏陀』『ルポ 誰が国語力を殺すのか』(いずれも文藝春秋)、『「鬼畜」の家』(新潮社)、『教育虐待 ~子供を壊す「教育熱心」な親たち』(ハヤカワ新書)など多数。2021年、『こどもホスピスの奇跡』で新潮ドキュメント賞を受賞。
企画担当
関 和佳代 (株)パセイジ