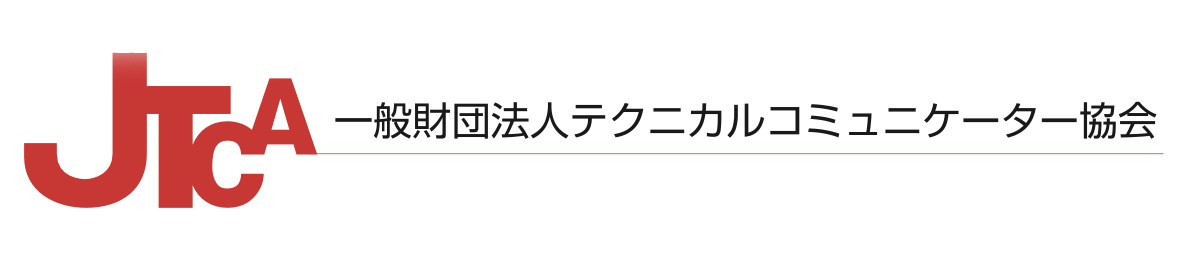25-TC21【ワークショップ】
真の説明力を鍛えよう
~言語技術が切り開くコミュニケーションの基礎能力~(2025.10.02更新)
セッション時間 TCシンポ2025 10月8日(水)14:00-16:30
対象とする聴講者
コミュニケーションエラーに悩む、すべてのテクニカルコミュニケーター
- 利用者用情報の制作に関わるライター、編集者、翻訳者
- テクニカルコミュニケーターの育成担当者
- 制作を統括するディレクターやマネージャー
- 言語化が苦手なエンジニア など
セッションの企画意図と概要
グローバル社会で働くテクニカルコミュニケーターにとって、自らが作成する情報を的確に「伝える」ことは必須のスキルである。しかし、「伝わる」情報を発信するまでに時間を要したり、受け手から期待した反応が得られなかったりすることは少なくない。その背景には、言語技術の不足が透けて見える。
欧米の言語圏では、小学生の段階から“言語技術=ランゲージ・アーツ (Language Arts)”を学び、考えを言語化する力を鍛えている。一方、日本では同様の教育を受けられる機会が限られているため、高等教育に進むにつれて、さらには社会人になると、「書く力」はもとより言語化能力の不足に悩む機会が増えている。
本セッションでは、「聞く・話す・読む・書く」の言語の4機能に加え、これらを下支えする「分析し、考える力」を重視する言語技術を学ぶ。その有用性は、現場の教師も学びを求めるほどである。
座学のあとのワークでは、情報を明確かつ論理的に伝えられる『パラグラフライティング』を実践形式で学び、本セッションの理解度を確認できる。ここに含まれるのが、要素出し、カテゴライズ、構造化、アウトライン、記述の手順の学びである。
パラグラフライティングは、テクニカルコミュニケーターに求められる構成力の向上に寄与し、生み出される情報は読み手の理解を深める。
コミュニケーションの基盤強化に欠かせない「言語技術」を学び、実務で役立つ「伝わる文章作成」の基盤構築を目指してほしい。
【参考】教師たちの学びを紹介した記事:Wedge ONLINE
予定しているワークショップの内容
座学のあと、ワークに取り組みます。(進行状況に応じて、グループワーク形式を取ることがあります)
- 言語技術の概要
- アメリカやドイツで行われている言語技術教育の現状
- テクニカルライティングに求められる文章
- テクニカルライティングに必要な言語技術
- ワーク①
- ワーク②
受講者に準備いただくもの
ワークの結果を原稿用紙に記述し、考えを言語化します。〈当日の資料〉に加えて、以下を持参してください。
- 筆記具(数色のペンを推奨)
- 用紙(A4サイズ程度)数枚
- 付箋紙(1.5cm×5cmサイズを推奨):単色でもかまいませんが、複数色の使い分けを推奨します。
- 横書き用400字詰め原稿用紙を数枚:字数確認のために、A4用紙とは別に準備いただくことを推奨します。
定員
30名
当日の資料
ダウンロードして、必ず持参してください。
お申込みされた皆様には、ダウンロード用のパスワードを別途メールにてお知らせいたします。
なお、パスワードの共有はご遠慮ください。
講師
三森 ゆりか (有)つくば言語技術教育研究所
プロフィール
つくば言語技術教育研究所所長。東京都で生まれ、中学2年生からの4年間を旧西ドイツで過ごす。帰国後、上智大学外国語学部ドイツ語学科で学ぶ。卒業後、商社勤務を経て平成2年、つくば言語技術教室(現・つくば言語技術教育研究所)を開設。西ドイツで学ぶ中で、ドイツ語習得に関しての反省に気づく。そこから、言語技術の重要性に着眼し「日本語による言語技術教育」を開発した。様々な教育機関や、日本オリンピック委員会や日本サッカー協会をはじめとするスポーツ団体、東日本旅客鉄道や西日本旅客鉄道、日本航空などの大手企業からの要望を受け、企業研修を精力的にこなす。平成17年度文科省読解力向上に関する検討委員会委員、平成18~19年度文科省言語力育成協力者会議委員として、日本語教育の課題に関する提言を続ける。絵本からビジネスマン本までの幅広い著書からは、言語技術教育が対象とする層の広さがうかがえる。なお、東京で年2回開講している一般人対象の「大人講座」には、これまで多数のIT関係者が参加している。
企画担当
村田 珠美 (株)三六六